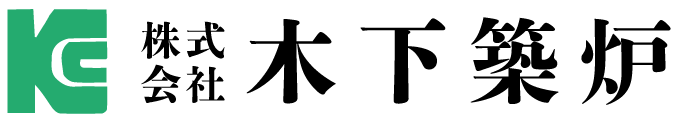いつも弊社のコラムをご覧いただき、ありがとうございます。
本日は私が考案した『勤務評価判定装置』が、令和7年9月19日付で実用新案として正式に認められたことを皆様にご報告させていただきます。
ですが本題に入る前に少しだけ、過去に取得した実用新案についても紹介させてください。実は今回の登録は4案目となり、最初はお棺を載せる台車運搬機の静音化に挑戦。
2度目の出願となった『自動化耐火物混錬機』では、予め設定した材料比率に基づき耐火物に自動で水分の混合・混練を行うため、手作業での流し込みが不要となり、常に安定した施工体の製造が可能となりました。
そして3つ目が火葬後のご遺骨を散骨や手元供養、ときには墓じまいといった要望に応じて直径2mm以下に粉骨する『Grinder(グラインダー)』。この粉骨機は大分大学と共同で取り組むJICAによる国際プロジェクト、フィリピンでの狂犬病関連死の根絶を目指して導入した動物用火葬炉にも併設しています。
そしてこの度、新たに登録を受けたのが『勤務評価判定装置』。
私は2年前より世代交代に向けた準備を進めてきましたが、後継者による人事評価では透明性や公平性の確保が重要だと考えてきました。しかしながら従業員の評価を客観的に導き出すことは、具体的な数値がない限り難しいもの。特に弊社には外国人労働者が多く在籍することから、どのようにすれば言語の異なる彼らの勤務意欲や勤務実態を正確に把握できるのか。“測ることが難しい数値の可視化”は、事業継承の前に解決したい大きなテーマのひとつでした。
そこで自己・他者評価の両方を得ることができ、その結果を業務やマネジメントの改善につなげられる独自のアプリを考案。
外国人就労者が月に1度、スマートフォンを通して申告する自らの勤務意欲については、「資格をとって最大8年は定住を目標に仕事をします」「契約期間だけで帰ります」など、5つの選択肢の中から現在の心境に合わせた回答を選べるようにました。
さらに正しい勤務実態を明らかにするため、技能実習生には自分以外の外国人労働者全員の評価も行ってもらうことに。ここでは「安全規則を守っている」「仕事に対して積極的である」など10項目にわたる質問があり、それぞれに5点満点の評価尺度を適用。入力期日の遅延が目立つ従業員には声を掛け、評価スコアが一定の基準に達した場合は面談を実施しています。
私たち日本人は仕事ができる人に技術を教えようと動くことが多いですが、長い目で見ると“長く働く意欲のある人”を育てる方が組織にとって大切だと思いませんか?
会社にとって真に熟したものは何か?と考えたとき、たとえ今は不器用でも2〜3年かけて一生懸命に資格を取り、8年間後の会社の成長に貢献できる意欲的な人材にこそ投資をしたいと考えたのです。
人口減少と高齢化が進行する日本では、外国の働き手の力を借りなければ仕事が成り立ちません。弊社でも慢性的な人手不足が続き、以前は国内の人材派遣サービスを活用していました。過去には現場を担うメンバーのうち2名が弊社従業員、残る6名は派遣社員という深刻なときも。非正規社員への依存は人件費の上昇として経営に重くのしかかりますが、会社の存続を考えれば仕方がなかったのです。
けれどそんな悩ましい時期に検討を重ね、結論として導き出したのがターゲット人材層の拡大。これまで受け入れてきた技能実習生の姿を振り返ると、基本作業においては日本人労働者と遜色がなく、ときに若さという強みから能力を発揮するケースも見てきました。それならこのまま国内で求人を募り、応募を待ち続けるよりも外国人の雇用を検討した方が良いではありませんか。
でもその策を実行するのであれば、解消しなければならない問題がひとつ。
それは外国人労働者の増加に伴い、これまで以上に組織の中で顕著になる言葉や文化の壁です。これらの課題を解消して円滑な関係を築くためには、技能実習生と日本人従業員との間に立つ人間の存在が有効であると考えました。
そこで私はフィリピンへ行き、かつて弊社で働いてくれた1〜3期生の中から信頼のおける人材をピックアップ。「これから多く迎える予定の技能実習生と日本人従業員の間に入り、先輩としてクッション役を果たしてもらえないか」と打診をしたのです。すると返ってきたのは、嬉しいことに前向きな答えでした。そして2年が経った今、役割を引き受けてくれた3人は現場の課題や意見を収集し、私にフィードバックをくれています。
そしてその上で新たに必要性を感じたのが、今回の勤務評価判定装置というわけです。
公正な評価の実現はもちろん、アプリに入力されたデータは、雇用継続が困難になった場合、企業が正当な理由を証明する記録となりうると私は考えます。もちろん今までそんな主張をしたことはないですし、今後もそういったことが起こらないことを望みます。
ですが外国人材への依存度が高まる中、“技能実習生は原則として契約期間中に解雇することはできない”という従来通りの規定は雇用主にとってリスクであることは間違いありません。勤務評価判定装置はそんな制度に一石を投じる手段にもなるのです。
さらに弊社ではアプリを日本人従業員の評価にも活用しており、採点者は外国人実習生全員と決めています。忖度のない立場の人間による評価は、客観的・多角的な視点をもたらし、結果として公正さを生むと考えるからです。
ただしその得点が反映されるのは、あくまでも個人の成果や貢献度に基づいた昇給部分のみ。業績の向上を平等に還元する、会社の利益に紐づいたベースアップの部分に外国人実習生による採点結果が連動することはありません。
世代交代に伴う人事評価のバトンを、従業員の誰もが納得するかたちで後継者に引き継ぐためにも。日本人と外国人実習生が手を取り合い、より良い関係を築いていくためにも。この勤務評価判定装置が不透明な評価基準からの脱却剤となり、組織活性化の鍵となることを期待します。